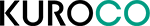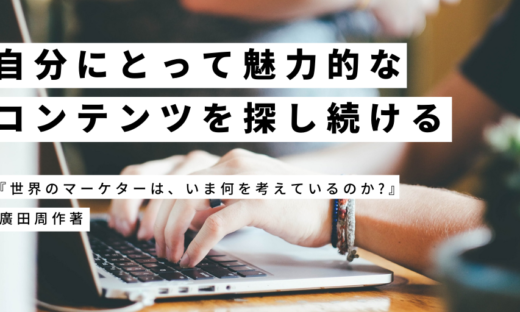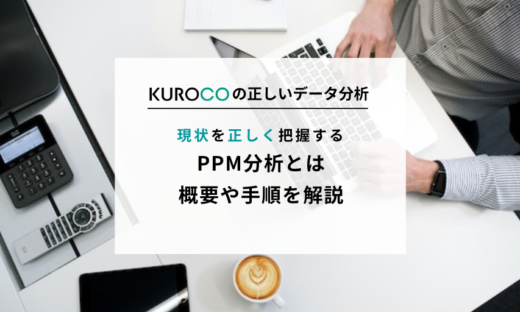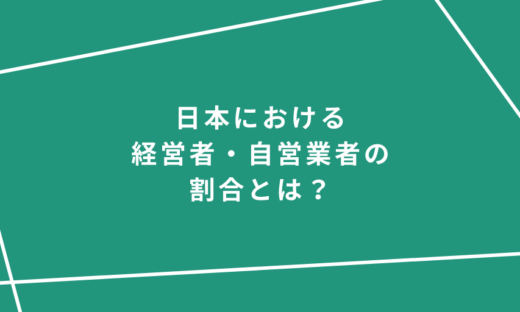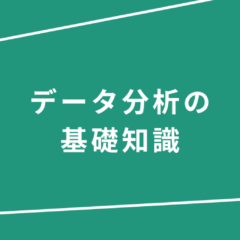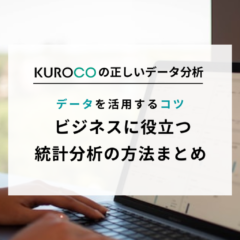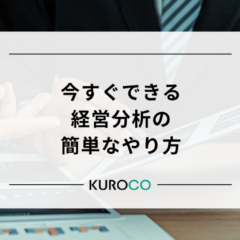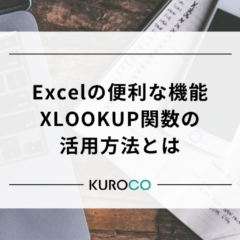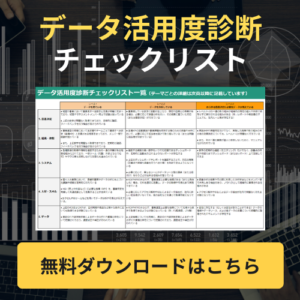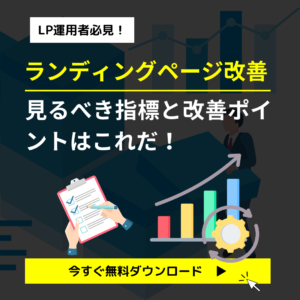スモールビジネスで成功するために必要な考え方とは? | マイケル・E. ガーバー著 はじめの一歩を踏み出そう

こんにちはKUROCO株式会社代表の齋藤です。
『はじめの一歩を踏み出そう―成功する人たちの起業術』は旧版もあわせて、20カ国語で翻訳され100万部以上の売上実績を持つ E-Myth Revisted の邦訳です。
著者のマイケル・E. ガーバー氏は、25000社もの中小企業(スモールビジネス)に対してアドバイスをしてきた経営コンサルタントで、本書ではコンサルティング経験の中で培われた「スモールビジネスで成功する(失敗しない)」法則・考え方・やり方について説明しています。
このマイケル・E.ガーバー氏から直接コンサルティングを受けて、現在日本で本人の許諾を得てそのノウハウをコンサルティング商品として中小企業向けに支援をしている社長と出会い、読んでみました。
経営にも法則がある
サッカーや野球などのスポーツや、国語や算数といった勉強など、何でも上手になるためには一定の決まった法則、やり方あるのと同様、企業経営においても上手になる(=失敗しない、成功確率を上げる)法則ややり方があります。
その法則が7つのステップであると説明しています。
① 事業の究極の目標を設定(経営者である自分自身の人生の目標)
② 戦略的目標の設計
③ 組織戦略
④ マネジメント戦略
⑤ 人材戦略
⑥ マーケティング戦略
⑦ システム戦略
重要だと思った点は、まずは①です。そもそも自身の人生の目標があってこその事業だということ。これが事業=自分の目標となってしまっているケースが多くなってしまっていると感じました。自分(個人)と企業(法人)はその名の通り人格が異なります。これを同一化せず、企業も自身の人生をより幸せにするための一つの方法だということを認識することが大切です。
とは言え、経営者ですし好きでその事業をやっているため、その事業が自身の人生を豊かにするための大きな要素を占めるので、②事業の戦略をしっかりと定めることが重要になります。これは私自身もデータ分析する際に常々言っていますが、目標(目的、ゴール)なければ何もできないということです。
面白いなと思ったのは、その後の③④⑤です。企業経営していく上では、「人」がとても重要だということを再認識しました。
個人事業主であれば別ですが、企業経営をしていく以上、自分以外の人の協力が不可欠です。特に経営者がいなくても滞りなく事業が回っていく企業とするためには、組織をどうするか、その組織をどうマネジメントするのか(いかにモチベーション高く人が積極的に動くのか)ということの重要性を学びました。
その上でマーケティングがあり、システムがある、この順番はとても重要だと感じたので、意識していきたいです。
多くの経営者の間違い
私含めて、会社を興す際に、今まで自分で培ってきた知識やノウハウ、他人よりも優れているだろうと思っていること、得意なことを武器とし、夢を描きます。一方、今では好きなことを自分の仕事にする人も増えています。そしてその得意なことや好きなことをとにかくやっていけば経営できる、事業を回せると思っている人が大半かと思います。
しかし本書では、それでは経営できないということを強く述べています。
確かに私自身、ずっとコンサルティング畑で、今ではデータ分析をビジネスとしていますが、このデータ分析の部分は、なかなか自分の手元から離せずにいます。いわゆる職人になってしまっている、ということです。
本来経営者の仕事とは、その名の通り経営、いわゆるマネジメントをすることなので、会社の事業をマネジメントすることが重要で、会社の事業の実務部分を多く担ってしまうと拡大成長は難しいのだと思います。
私自身もそこは痛感しており、現在は今まで手でやってきたデータ分析という業務を「分析・可視化ツール」として世の中に広めていこうとしています。この方法は間違ってはいないことだと再認識しましたが、まだまだ自身の依存度が高いため、そこの脱却は不可欠だと感じています。
とにかく仕組化・ルール化・マニュアル化
もちろん自身が好きで仕事をしているので、仕事しない、という訳ではないですが、経営者自身がいなくても事業がまわっていく企業とすることはとても重要だと思います。
そのためには、一定の条件は必要なものの、誰でも出来る仕組化、ルール化、マニュアル化が必要となります。
本書では、「フランチャイズ」にその要素が詰まっていると説明していますが(フランチャイズビジネスをしましょう、という訳ではない)、結果として、オリジナルで経営している企業よりもフランチャイズに加盟して経営している企業の方が圧倒的に廃業率が低くなっています。
そこには徹底された仕組化、ルール化、マニュアル化が存在するからとなります。
弊社であれば、力を入れて展開しているEC-DashBoardにおいて、
- マーケティング方法(検証・改善)の仕組化
- 営業(商談)のマニュアル化
- 成約後の顧客コミュニケーションの仕組化、マニュアル化
- EC-DashBoardの使い方や機能のマニュアル化
- EC-DashBoardにおける月次レポートのルール化
などが必要だなと感じています。
これは経営者自身が実務として担っている部分だけではなく、他のメンバーが担っている業務についても仕組化・ルール化・マニュアル化をすることで、究極、全員が入れ替わっても回っていける事業となるか、というところまでやり切れるととても強いと感じました。
とは言え、それだと面白味もなくなるので、そこを目指しつつも、今いるメンバーならではの個性や特徴があるからこその企業だと思っています。
まとめ
言われれば「確かにそうだよな」と思われる内容でもありますが、これがなかなか出来ないのが実態ではないでしょうか。特に中小企業(スモールビジネス)はもともと経営者が立ち上げ経営者が自身で売上を作ってきており日々の業務で多くの時間を取られているケースが多いです。そこから徐々にとは言え、仕組みを作りながら組織を形成していく、マネジメントに比重を置いていくのはかなりパワーのいることかもしれません。しかし、本書に書かれているように、それでは事業を成長させていくための経営とはなりません。
スポーツや勉強、そして自身が今まで培ってきたビジネスと同様、経営にも法則があります。それは私自身も経営している身として感じています。
経営の法則について学びたいという方は、25000社もの企業にアドバイスをしてきて、2000年には起業家向けアンケートで7つの習慣、ビジョナリーカンパニーを抑えてビジネス書ランキング1位に選ばれ、かつ今でも読まれ続けている本書を一度は読むことをお勧めします。