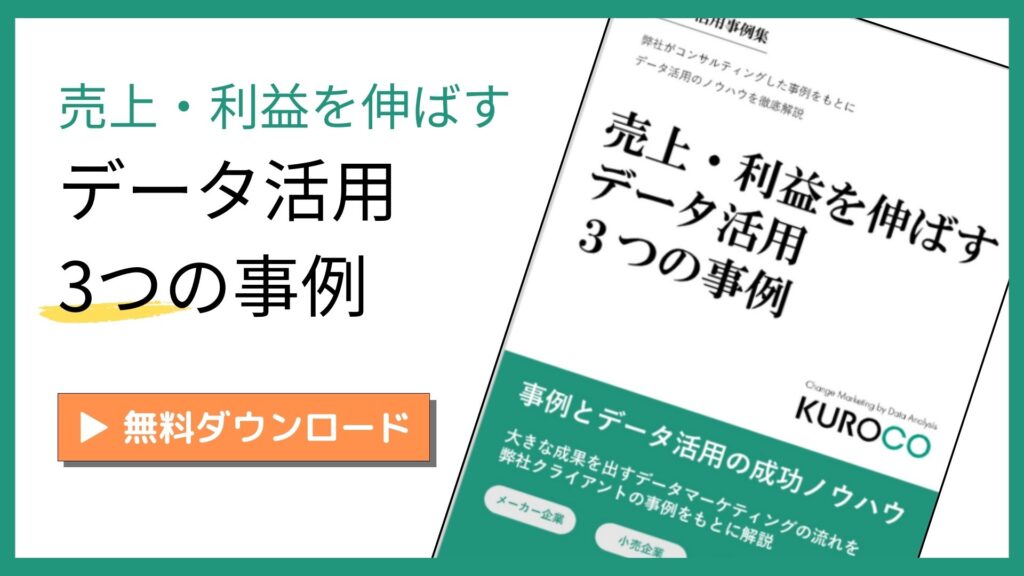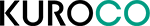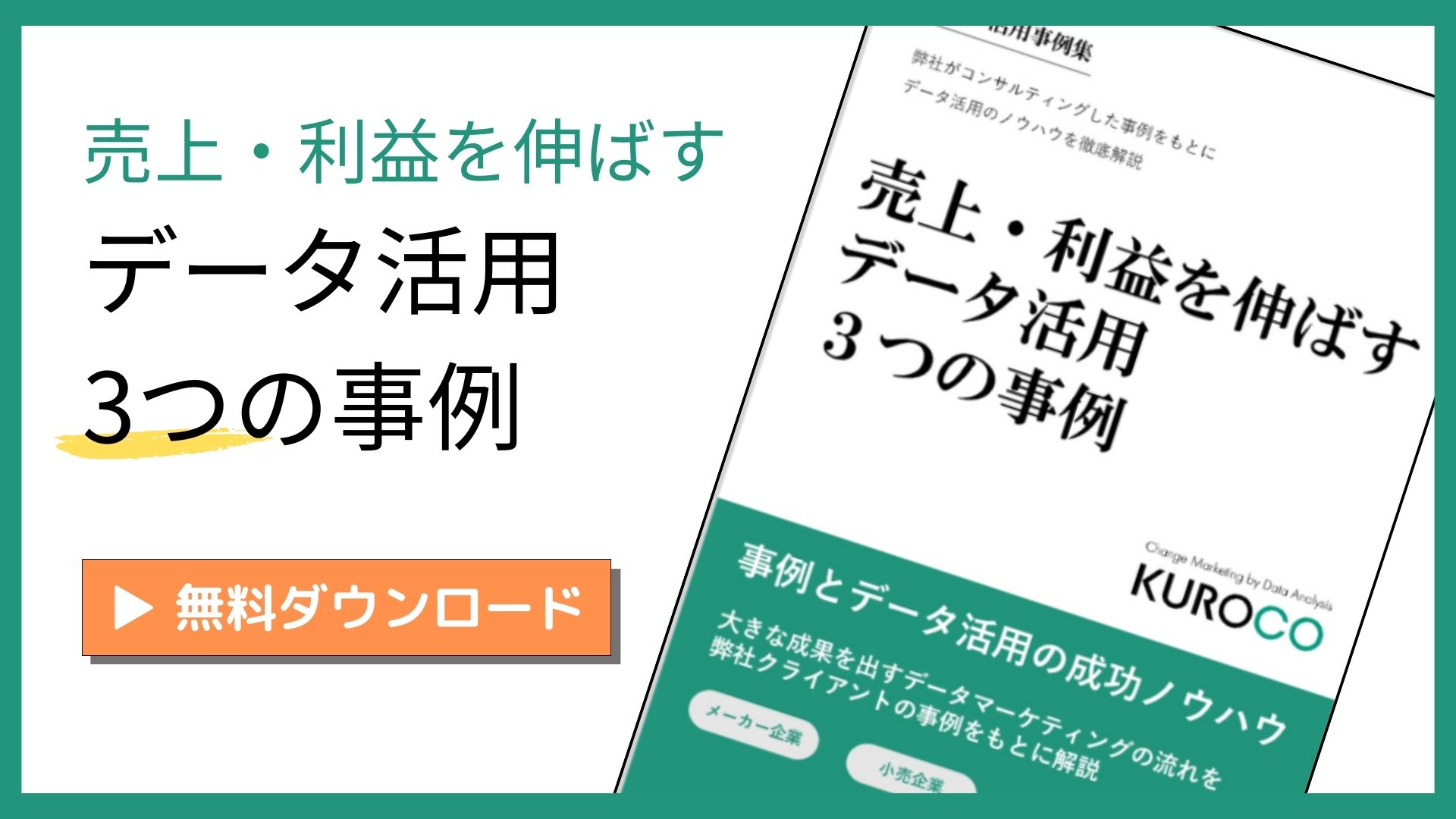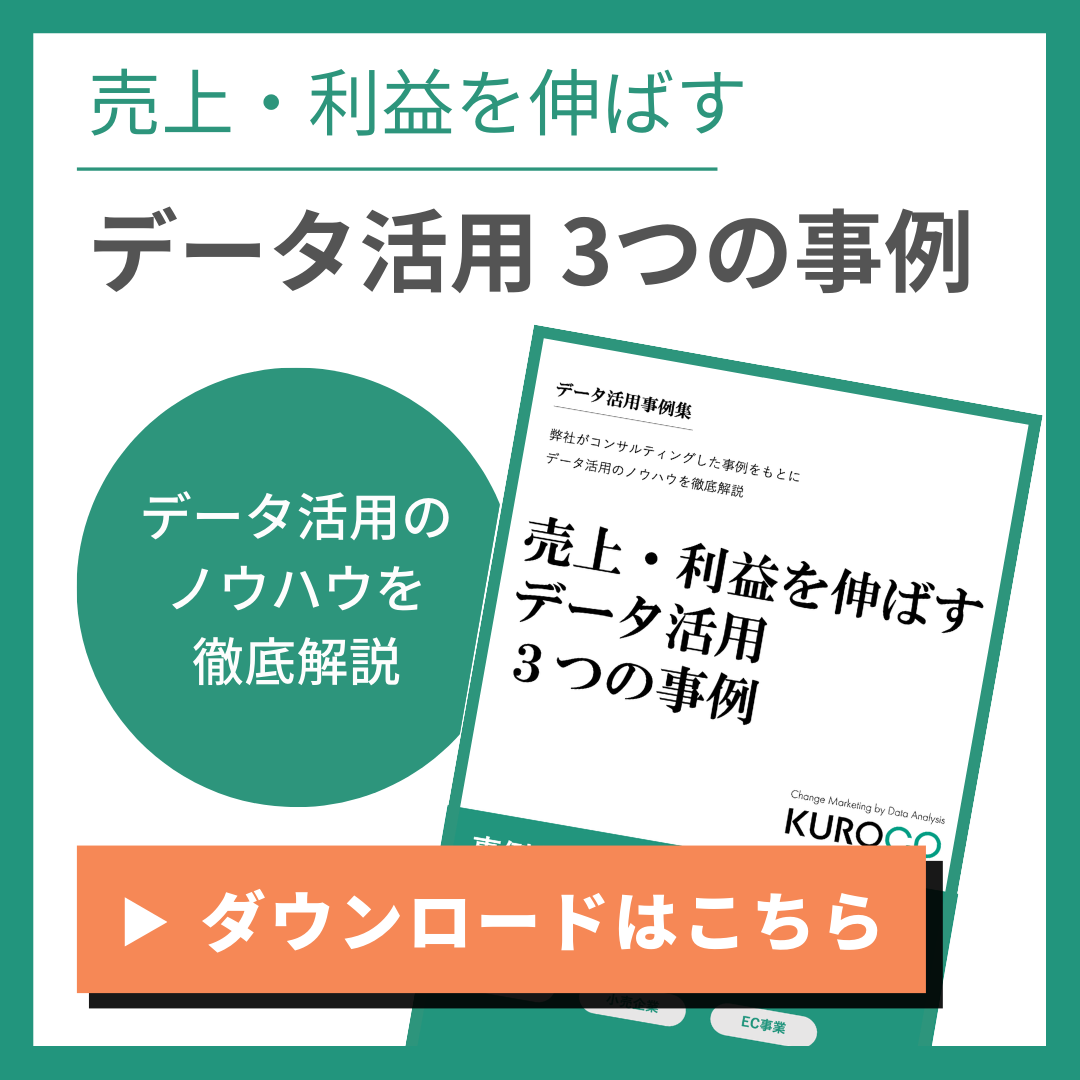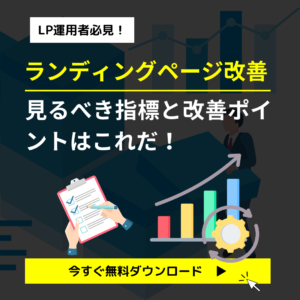顧客軸でのデータ分析で成長余地を算出!生活雑貨メーカーのデータ分析事例

この記事では、弊社クライアントの事例をもとに、顧客(取引先)軸でのデータ分析事例をご紹介します。
目次
この記事を読んでいる人がよくダウンロードしている資料
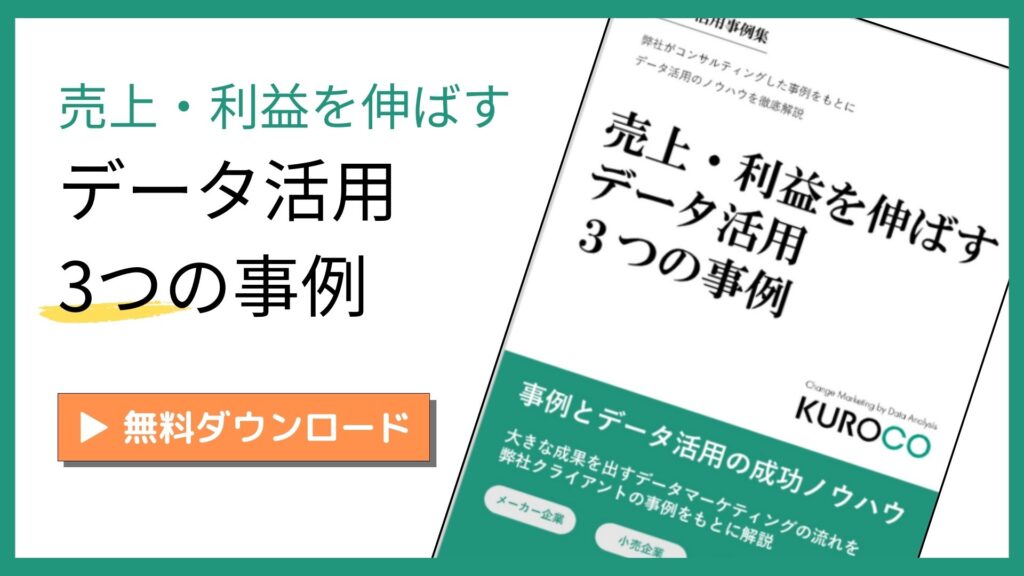
業績推移から現状を把握する
生活雑貨メーカーD社は、ディスカウントストアやドラッグストア、スーパーやコンビニ等へ自社商品を卸販売している企業です。
図表1のように、年々売上が減少しまっている中、依頼を受け、データ分析しました。
図表1 D社の業績推移

図表1の左側は売上推移で、毎年平均8.2%減少で推移していることが分かります。右側のグラフは売上を売上数量と商品単価に分解してそれぞれの推移を表しており、商品単価については若干増加している一方で、売上数量が年々減少していることが分かります。D社は卸先への販売数量が減少したことにより、売上を大きく落としていることが分かります。
D社の事例では、この売上減少要因について、様々な分析を行いましたが、本書では「顧客(取引先)軸」でのデータ分析についてご説明します。
また、その分析結果に基づき、今後どの程度の成長余地があるのか、売上ポテンシャルを算出する方法についてもお伝えしていきます。
データ分析で売上減少の原因を見つける
さて、D社についてデータ分析を深掘りしていきましょう。
図表2を見ると、ディスカウントストア(家電量販店含む)と31期からスタートした直営店を除いて売上減少しています。
図表2 D社の取引先の業態別の売上推移

また、33期と34期を比較すると、ディスカウントストアと直営店も含めて、全業態で売上減少していることが分かりました。取引先の業態別で多少のバラつきはありますが、どこかの業態に偏って問題がある、というよりかは、D社全体として競争力が落ち込んできている、ということが言えそうです。
ちなみに、図表2の取引先の業態の区分については、D社内での区分方法になるので、皆さんの会社で分析する際には、自社で区分している方法で構いません。
市場環境と照らし合わせる
更に詳細分析をしていく前に、市場環境を見てみましょう。
売上推移を分析する際、減少している場合も増加している場合においても、市場の成長性と比較して自社売上の成長率が高いかのか低いのかといった視点が必要です。
- 自社の売上成長性よりも市場成長性の方が高い
→競合他社にシェアを奪われている可能性あり - 自社の売上成長性と市場の成長性が同程度
→市場の成長に伴い自社も成長 - 自社の売上成長性の方が市場成長性よりも高い
→競合他社のシェアを奪えている可能性あり
従って、自社が展開している商品やサービスの市場規模の推移を調べることもとても重要です。推移までは分からなくても現時点の大体の市場規模が分かるだけで、自社が現時点でどの程度のシェアを獲得できているのかが分かります。それだけでも今後の成長余地などのイメージが付くでしょう。
D社が展開している生活雑貨商品の市場規模の推移を見ると(図表3)、ほぼ横ばいであることが分かりました。
図表3 D社が展開している生活雑貨商品の市場規模推移

D社の売上は大きく減少傾向で推移しているため、D社の競争力が相対的に落ちていることが分かります。
ちなみに市場規模の調査方法ですが、各業界団体や調査会社が市場レポートを作成していることが多いので、そちらを確認するのが最も多い手法です。もちろん調査方法を確認する必要はありますが、その情報を販売することを事業として展開しているため、蓋然性は高い情報と言えます。
もう一つの方法として、総務省統計局が、一世帯当たりの年間支出額を様々な品目で出しております。それに同じく総務省統計局が出している世帯数を掛け合わせることでも算出できます。業界の市場レポートの数値と総務省統計局からの算出数値の両方を確認できる品目であればぜひ両方とも調査してみてください。
さて、D社ですが、市場規模推移と比較して大きく売上減少しており、それを取引先の業態別に比較した際に(図表2)、全業態において減少している傾向となっていました。
顧客(取引先)軸でのデータ分析
従って、顧客(取引先)軸において、また別の視点でデータ分析してみたのが図表4になります。
図表4 D社の取引先の売上傾向別の取引数と売上推移

取引先の売上傾向に応じて4つの分類に分け、それら分類ごとの取引先数(左グラフ)と売上(右グラフ)の推移を分析したのが図表4になります。
4つの分類ですが、
- 新規・復活:新たに取引が始まった、あるいは前年には取引がなく当期再度取引が始まった取引先
- 既存売上減少:前期よりも当期の売上が減少した取引先
- 既存売上増加:前期よりも当期の売上が増加した取引先
- 流出:前年に取引があったが、当期に取引がなくなった取引先
となります。
根本的な原因は”ロイヤリティの高い顧客との取引数”
図表4により、D社の根本的な問題が把握されました。その特徴が特に34期に表れているので34期について説明すると、
- 既存売上増加となる取引先や新規・復活の取引先が前期(33期)と比較して増加している一方で、既存売上減少となる取引先は減少している(左グラフ)
- 既存売上増加となる取引先の売上高は前期と比較して減少している一方で、既存売上減少となる取引先の売上高は増加している(右グラフ)
- 新規・復活している取引先や流出している取引先の売上は
- 既存の取引先と比較すると数%程度と微小(右グラフ)
となっています。
売上のほとんどを既存の取引先で構成されています。そして、既存売上増加となる取引先数が増加している一方で占める売上が減少している、その反対に既存売上減少となる取引先数が減少している一方で占める売上が増加しているということは、売上構成比の高い上位の取引先数が大きく減少してしまっている、と言うことです。
ロイヤリティの高い顧客との取引が薄くなってしまっていることが、D社の根本的な問題となります。
新規顧客も含めて売上増加している取引先数は多くなっていますが、取引金額が小さく、ロイヤリティの高い上位の取引先の売上減少をカバーするには至っておらず、結果として大きく売上減少し続けているのが、D社の現状なのです。
D社に必要なのは”本部商談のできる営業人材”と”有力な顧客へのアプローチ”
その現況を別の視点でデータ分析して検証したのが図表5になります。
図表5 取引先の取引金額順位別の売上構成比の推移

図表4で確認できた通り、D社は34期においては2,500社程度との取引があることが分かりました。しかし、図表5を見ると、34期においては上位10社で売上全体の30%を占め、上位100社で72%を占めています。
D社においては、この上位の顧客との取引が大きく減少してしまっていることが売上減少の一番の原因であり、再度上位の顧客との取引を増加させていけるかどうかが、売上減少を止め、再度成長するために必要なポイントであると言えるでしょう。
このような上位顧客の売上減少を引き起こしてしまっていた要因として、「有力な顧客との本部商談が出来ていない」「要件を満たす営業人材の不足」といった営業カバレッジの不足、提案力の不足がD社に内在していました。
そこで、本部商談のできる営業人材を確保し、トップダウン含めて有力な顧客に対してアプローチをかけていくことで、売上増加を目指すことに決めました。
売上成長余地(売上ポテンシャル)の算出
では、それが実現できたとして、どの程度の売上成長余地があるのでしょうか。また、それを実現する上で、どのようにターゲット顧客を定めていけば良いでしょうか。
最後は、この売上成長余地(売上ポテンシャル)を算出するためのデータ分析についてご説明します。
図表6は主なディスカウントストアおよび家電量販店の各企業の売上高とD社がそれらの企業と取引があるかどうかを示した表になります。
図表6 主なディスカウントストア・家電量販店の企業売上とD社の取引実績有無

D社はビジネス特性上、上場しているような大手企業が取引先として多いので、図表6のように、売上数値を各企業のIR情報等から取得できます。上場していない企業でも、自社のHPで売上高を公開している企業があるので、そちらも確認してみると良いでしょう。
また、SPEEDA(スピーダ)という経済情報プラットフォームがあるのですが、こちらを使うと、同業界の企業の業績一覧が見れたり、業界情報や市場規模等のデータも簡単に取得できるので、利用してみるのも良いと思います。それでも企業の売上が取得できない場合は、帝国データバンクや東京商工リサーチが企業情報をデータベース化しており、有料にはなってしまいますが、ほとんどの企業の業績データを取得することはできます。
また、商談時において、必ず商談先の企業の売上規模をヒアリングすることを徹底してください。売上規模は営業先の優先順位を付ける上での一つの指針となります。
もちろん全ての企業が教えてくれる訳ではありませんが、売上規模やそれに準ずる指標(例えば従業員数等)を把握しておくことはとても重要です。
ではD社に戻りましょう。
図表6を確認すると、主なディスカウントストアや家電量販店において、トップのヤマダ電機はじめ、半数以上とは取引があることが分かります。従って、今まで取引が発生していない企業に対しては、アプローチをかけることで取引できる可能性があると推測できます。
では、どの程度の取引が目指せるのかを次に分析します。
図表7は、先ほど図表6で表示した企業のうち、D社が実際に取引のある企業について、次の2つの軸で30期と34期をプロットしたものになります。
図表7 主なディスカウントストア・家電量販店の企業売上とD社売上シェアの推移

横軸:取引先企業の企業売上
縦軸:取引先企業の企業売上に対するD社の売上シェア(単位であるppmとは、百万分率で、100万分のいくつであるかを表します)
図表7より、取引のある顧客によってもD社の売上シェアにバラツキがあることが分かります。
図表7については、ディスカウントストアおよび家電量販店の業態なので、企業ごとに違いはあるものの類似した商品構成となっています。
従って、最も売上シェアの取れている取引先と同程度までは売上が取れる可能性があります。売上成長余地を算出する上で、MAXケースを最も売上シェアの取れている取引先と同程度の売上シェアまで取れるとし、BASEケースを売上シェアの低い取引先において、同業態の取引先における売上シェアの平均値まで取れるとすると良いでしょう。
D社の場合は、一部の顧客であるドン・キホーテやラオックス、ビックカメラ以外の取引先においては前述3社の売上シェアと比較するとかなり低いので、まだまだシェアを上げられる可能性があります。また、同3社においてもビックカメラを除いて30期から34期にかけて売上シェアが低下しているため、売上シェアが高かった30期レベルにまで改善できる可能性もあるでしょう。
このように、企業ごとに自社の取引有無の調査と、取引先ごとに企業売上と自社の売上シェアを比較することで、今後どの程度の売上成長余地(売上ポテンシャル)があるのかを分析することができるのです。
\ この記事を読んでいる人におすすめ! /